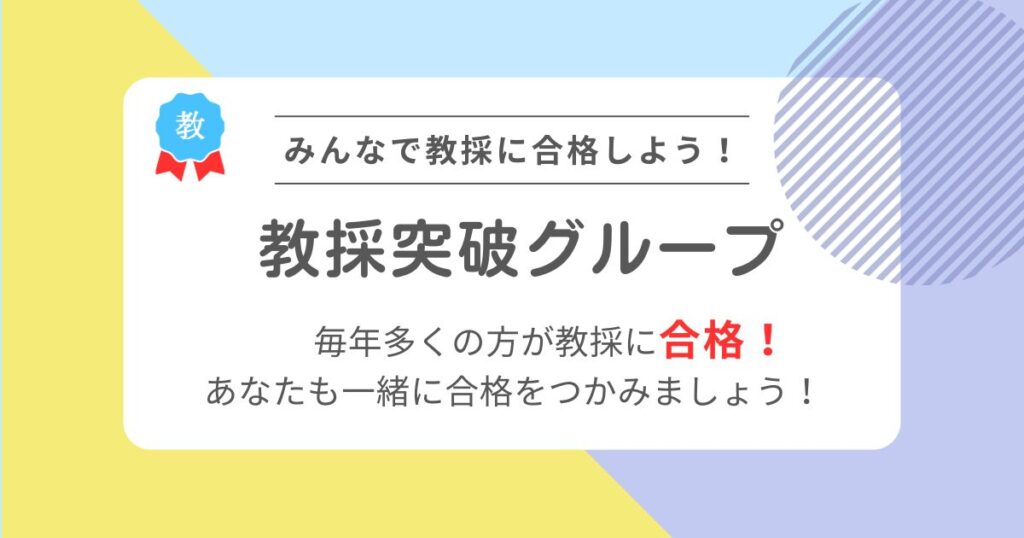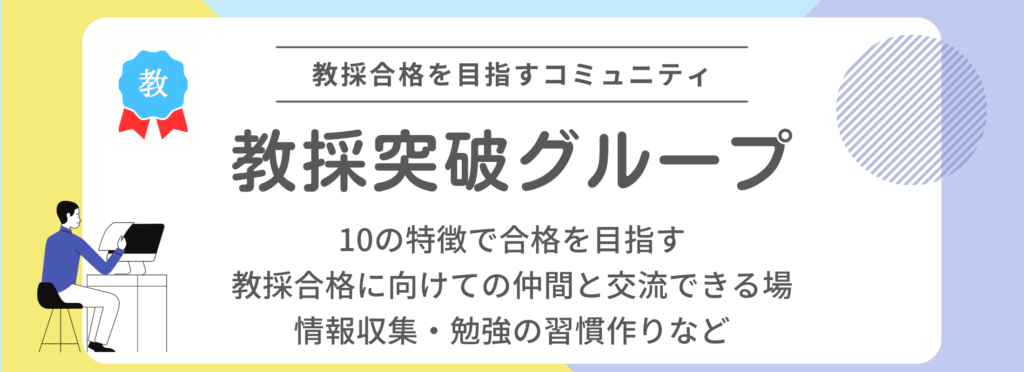「ふるさと島根を学びの原点に未来にはばたく心豊かな人づくり」
という基本理念の島根県。県の職員採用情報(教員)ページから、様々な情報を知ることができますので、島根県のことを調べつつ対策をしていきましょう。
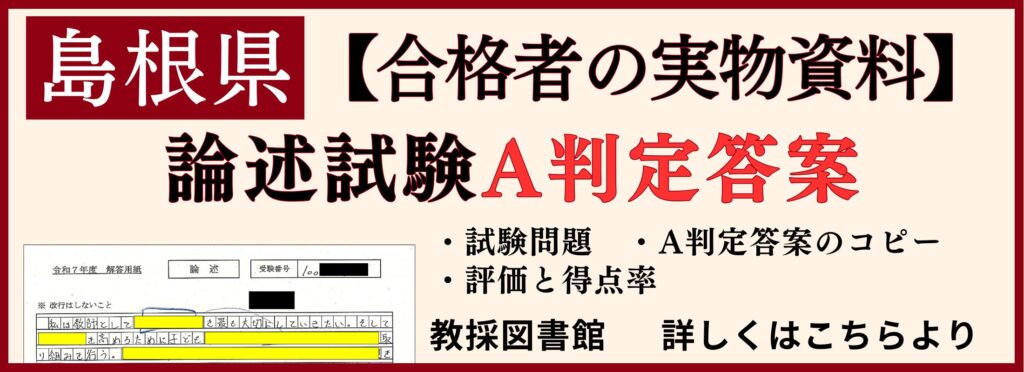
この記事を書いた人

- 教採塾ブログ管理人
- 教採対策サークル主宰
- これまでに多くの合格者を輩出
- 教員経験 小学校・中学
X:https://twitter.com/isshi_ec
教採情報や教員お役立ち情報を発信
フォローよろしくお願いします。
公式LINEでも教採に役立つ情報を発信中。
お友達追加するだけで対策資料4つを
🎁無料プレゼント🎁
ぜひお友達登録をお願いします😃
試験の変更点
以下の変更点があります。
詳しくは島根県公立学校教員採用試験のアウトライン、募集セミナー動画でご確認ください。
- 島根創生特別枠の受験区分の変更
・中学校での受験可能 - 出願要件等の変更
・中学校「社会人を対象とした選考(特別免許状による採用)」の新設
・併願制度の拡大 - 受験機会の確保
・第1次試験で福岡会場を新設
・第2次試験で大阪・東京会場を設定(小学校のみ)
・第2次試験の追試験を実施 - 受験上の特例措置の変更
- 特別選考試験
・5月上旬の連休中に実施
・私立学校の正規教員も対象者に追加
島根の教員として求められる基本的な資質・能力
島根県は求められる資質・能力を5つの柱で挙げています。
(説明会資料より)
1 豊かな人間性と職務に対する使命感
●人間理解・人権意識
生命尊重・人権尊重の精神と、多様な価値観を尊重する
●態度を有している
職務に対する誇りと責任
教育職員として必要な倫理観、職務に対する使命感・責任感、学び続ける意欲を有している
●ふるさとを愛する心
地域の自然・歴史・文化・伝統を理解し尊重する態度、ふるさとを愛する人材育成への意欲を有している
2 子どもの発達の支援に対する理解と対応
●子ども理解・子ども支援
発達段階を踏まえた子ども理解・子ども支援、キャリア発達に必要な基礎理論・知識を習得している
●特別支援教育の推進
特別な支援を必要とする子どもへの指導に関する基礎理論・知識を習得している
3 職務にかかわる専門的知識・技能及び態度
●教科等の指導に関する専門性
教育課程の編成、教科等の指導方法に関する基礎理論・知識を習得している
●社会の変化への対応
新たな学びや教育課題に対して、積極的に挑み試行錯誤しながら粘り強く取り組む意欲や探究心を有している
4 学校組織の一員として考え行動する意欲・能力
●学校組織マネジメント
学校教育の社会的・制度的・経営的理解に必要な基礎理論・知識を習得している
●他者との連携・協働
集団で活動する際、自己を成長させようとする意欲や態度を有している
5 よりよい社会をつくるための意欲・能力
●地域資源の活用と地域貢献
学校教育活動を通して、地域社会に貢献することについて、自分なりの考えや意欲を有している
●合意形成に向けた議論の調整・促進
子ども同士の話し合いの場面において、適切に働きかける力を有している
これらのことが求められています。
倍率と採用予定数
去年の合格者数と今年の採用予定数を比べてみましょう。
実施要項より。
| 校種 | 募集人数 | 去年の募集人数 | 採用数 |
| 小学校 | 150名程度 | 150名程度 | 同程度 |
| 中学校 | 110名程度 | 90名程度 | 増 |
| 高校 | 40名程度 | 38名程度 | 同程度 |
| 特別支援 | 25名程度 | 25名程度 | 同程度 |
| 養護教諭 | 10名程度 | 10名程度 | 同程度 |
| 栄養教諭 | 2名程度 | 1名程度 | 増 |
| 障害のある方 | 3名程度 | 3名程度 | 同程度- |
| 合計 | 340名程度 | 317名程度 | 増 |
募集人数は去年よりも23名多い340名程度です。減少する校種はなく、特に中学校では20名の大幅増となります。
気になる倍率ですが、去年の3.0倍よりも低倍率化することが予想されます。募集人数の増加もありますが、受験者数の減少が見込まれるからです。教員人気が低迷しているため、全国的に教採の受験者は減っています。
島根県の受験者数と倍率は次のように推移しています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| R元 | 997名 | 277名 | 3.6倍 |
| R2 | 1042名 | 284名 | 3.7倍 |
| R3 | 906名 | 302名 | 3.0倍 |
| R4 | 891名 | 294名 | 3.0倍 |
| R5 | 996名 | 327名 | 3.0倍 |
島根県の3.0倍は全国平均の2.9倍とほぼ同じ倍率で、試験としては高倍率とは言えない倍率です。とはいえ、油断は禁物です。しっかりと対策を取った上で試験に臨むことが大事です。もし不安な方は他都道府県の併願を視野に入れるのもいいでしょう。経験とチャンス、選択肢を増やすことができます。
【日本全国】66自治体の情報を集めまくって気づいたこと
教採対策オススメ書籍
教採の対策方法はいろいろあります。
・講座を受講する
・先輩に見てもらう
・対策のサークルに参加する
など。
その中でもお手軽かつ効果的なのが書籍での学習です。
・必要な知識が体系的にまとめられている
・1人で学習できる
・時間や場所の制限がない
・安い
と、メリットはたくさんあります。
もちろん本を読むだけでなく実際の練習は必要ですが、
読書で知識を学ぶ → 練習 → 読書 → 、、、
というサイクルをしていけば、練習の効果は倍増していきます。
教採対策のオススメ本をまとめています。
ぜひこちらも参考になさって下さい。
続きを見る
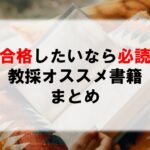
合格したいなら必読の教採オススメ書籍まとめ
筆記試験
筆記試験は教職教養と教科の専門教養が出題されます。
教職教養は日本国憲法や教育基本法などのいつの時代でも出題されるものから「こども基本法」「COCOLOプラン」など時代の流行で出題されやすいものまで様々です。
対策のオススメは最新の過去問を解くことです。
全国的にも出題の傾向は似ているので、受験先の自治体以外にも問題にあたってみることで確実な力をつけることができます。
また、教職教養の知識は面接対策に活きてくることも多いので、教職教養の対策は幅広くしておくと合格がより近くなります。
最新&問題数が多い過去問集がありますので、そのリンクを貼っておきます。
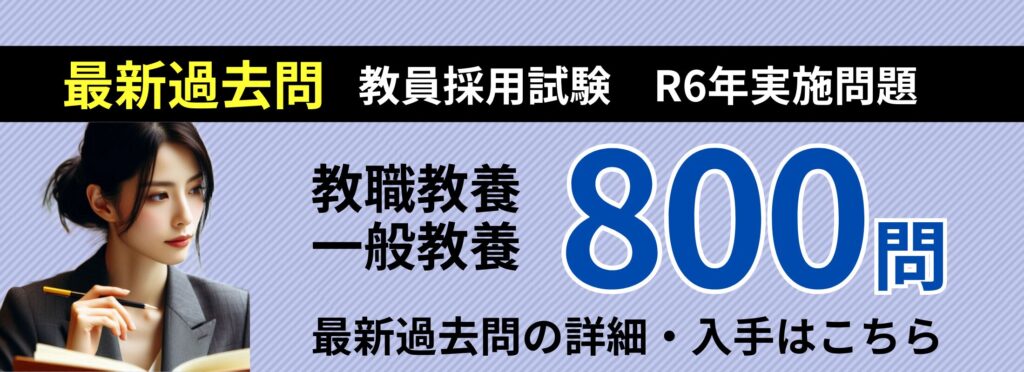
教科の専門教養は、その教科を指導するのに最低限必要な学力を有しているかを見るための試験です。ですので、そこまで高い難易度の問題は出題されません。
合格の目安は
小学校 → 公立高校の入試問題で6割取れるレベルなら合格点
中・高 → 大学共通テストで6割取れるレベル
です。
このぐらいが取れるのであれば専門教養で不合格になることはまずないでしょう。ただし、あくまで目安なので場合によってはそれでも届かない時もあります。対策はしっかりとおこなってしてください。
対策は過去問を繰り返し解くのがオススメです。
過去問は早めに買わないと売り切れて、再入荷まで数週間待たされることが多いです。過去問は早めに購入するか、売り切れの心配がなく即練習することができるデジタル過去問がいいでしょう。
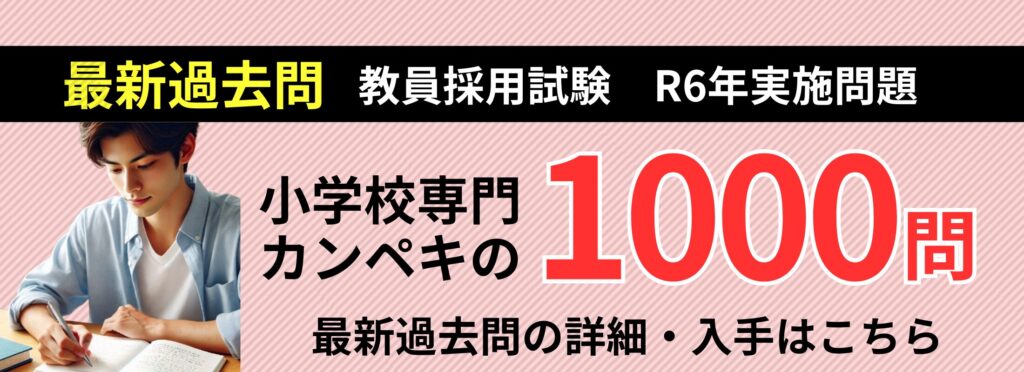
論述試験
第1次試験で論述問題が実施されます。
- 40分
- 350~400字以内
- 30点
40分で350~400字です。
時間に対して厳しい文量ではありませんが、余裕があるとも言えない時間です。テーマについて考察し、自分の経験を絡め、何を書いていくかを決めていきます。整った構成で書けるようにするには、ある程度の時間を必要とします。本番までには練習を重ねて、客観性や一貫性のある文章が書けるようにしておきたいところです。
例として設問を見てみましょう。
論述試験テーマ
令和5年実施
(問)教師として、あなたが特に大切にしたいことを3つあげ、それらについて350~400字で述べなさい。令和4年実施
引用 島根県公立学校教員採用候補者選考試験
(問1)次の空欄に言葉を入れて、子どもの学びの本質を端的に表す文をつくりなさい。
生きる力は( )がつくる。
(問2)空欄にその言葉を入れた理由を、300字程度で説明しなさい。
ここで重要なのは
- 挙げる言葉の選定
- 言葉を選んだ理由
これらを最初に考えてまとめることです。
最初の5~10分くらいなら時間を割いて考える価値は多いにあります。最初に文の構成を決めることで、文章の内容がブレにくくなり一貫性のある論文が書けるようになるからです。
論文が苦手な方は段落の見出しだけ考える練習をするのがオススメです。見出しだけなので短い時間でも練習することができます。
評価の主な観点
- 構成力
出題の内容をして、自分の考えを明確に述べているか。 - 論理性
分析と結論の間に論理性があるか。 - 表現・記述
語句の表現や記述が適切であるか。 - 発想
着眼点の良さがあるか。
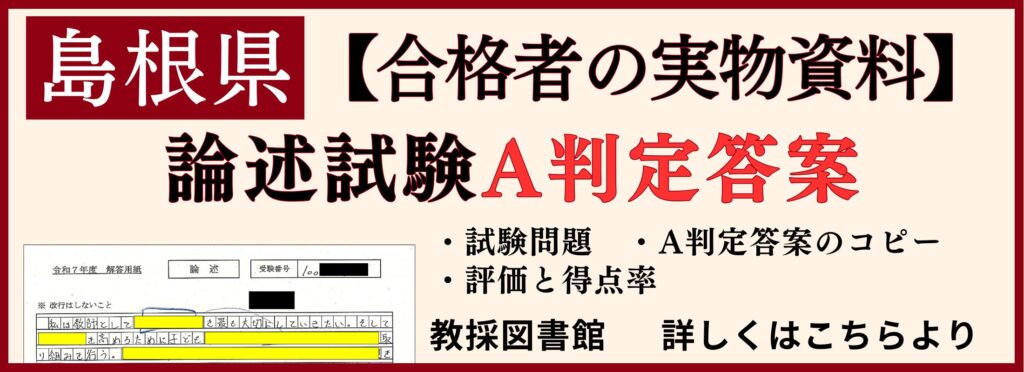
小論文の対策について、教採塾ブログでは小論文の添削をおこなっています。
A判定の取得経験のある専門スタッフが小論文を添削し、さらに
- わかりやすい文章にする秘訣
- 説得力ある内容にする方法
- 簡単に書くための型
をお伝えします。詳細は以下でご紹介しています。
また、何度も合格小論文を生み出した書き方を詳しく解説しているサイトが参考になります。
合格した小論文を無料公開している記事もあるので、書き方の参考になるでしょう。
また、小論文対策のオススメ書籍をまとめています。
こちらも勉強の参考にしてみてください。

個人面接
島根県では第2次試験で個人面接が行われます。
- 30分程度 × 2回
- 面接官3人
- 面接の中で「模擬授業(ロールプレイ)」「場面指導」を実施
評価の主な観点
- 教職への熱意
・教育に関する深い関心や問題意識を持っているか。
・教育公務員としての使命感はあるか。
・教員としての力を伸ばすために、継続的に自己啓発していく意欲があるか。
・児童生徒を深く理解しようとする意識や態度が見られるか。
・郷土を愛し、将来を担う人材育成への意欲が感じられるか。
・「主体的・対話的で深い学び」を意識した教育実践への意欲が感じられるか。
・新たな教育課題や教育方法に挑戦(探求)しようとする姿勢はあるか。 - 社会性・協調性
・広く社会的関心を持っているか。
・多様な価値観を尊重する態度があるか。
・それぞれの立場を考えながら発言できるか。
・周囲の人々と協調することができるか。 - 思考力・表現力
・物事を論理的に考えることができるか。
・広い視点からも物事をとらえ、考えることができるか。
・自分なりの考えをきちんと持っているか。
・思っていることを分かりやすく簡潔に要領よく話すことができるか。
・質問の趣旨に沿って、的確に答えているか。 - 人柄・態度
・円滑な対人関係を築くことができるか。
・今日一句における課題を前向きにとらえているか。
・明るく他人と接することができるか。
人権尊重の意識をもっているか。
質問内容
- 自己PR(3分)
- 教員の志望理由
- 島根県の志望理由
- 島根県の人口はどれくらいか
- 島根県の花は
- 島根県の国宝は
- 島根県を好きになったきっかけは
- 島根県を知った経緯は
- 島根県の人口に偏りがあることを知っているか
- 島根県が舞台になった古事記や日本書紀の話を知っているか。知っているならそれについて
- 島根県の教育の良さは
- 島根県の良いところは
- それを教育にどう活かすか
- 試験に向けてどの様な準備をしてきたか
- 大人のモラルをどう指導するか
- 課題を早くできた子が遅い子をばかにしている。どう指導するか
- あなたの長所は教育でどう活かされるか
- 図工科の基礎・基本とは
- 体育の授業を通して、子どもにつけさせたい力は
- 「一部の科目は生活で使わないのに、なぜ学ばなくてはいけないのか。」と子どもに聞かれたらどう答えるか
- 不登校の原因は何か
- 不登校の子にどう対応するか
- 特別支援教育で大切にしたいことは
- 教育実習で良かった経験は
- ボランティア経験は
- そこから何を学んだか
- 子どもを叱る時に気をつけることは
- 厳しい先生と穏やかな先生のどちらを目指したいか
→理由は - ストレス解消法は
- 今の心境を漢字1文字で言うと
- 教壇に立つときの気持ちを漢字1字で表すと
- 学力のキーワードは何か
- 「ふるさと教育」を具体的にどう取り組むか
- 学力低下に対してどう取り組むか
- 教師の大変なことは何か
- ケンカがあったらどう対応するか
- 保護者からのクレームにどう対応するか
- 英語教育で大事にしたいことは
- 保護者が学校に求めるものは
- 見が言えない子どもにどう対応するか
- 子どもの安全、安心を守るためにどうするか
- どのような子どもを育てたいか
- 授業で大事に思うことを一言で
- 5年担任だとして、箸の持ち方が指導しても直らない子がいる。保護者から「ほっといてください。」と言われたらどうするか
- 保護者に信頼される学校とは
- 言語活動をやる上で大切なことは
- 言語活動は活発だったが授業のねらいは達成できない授業と、言語活動はないがねらいは達成する授業。どちらがよいか
- これだけは子どもに伝えたいことは
- 10年後、どんな教師になりたいか
- 学級経営をする上で心がけたいこと
- 教師のやりがいを感じた体験
- 他の先生ではなく自分が担任することでどのような特があるか
- 自己啓発のためにやっていきたいこと
- 講師経験の中で大変だと思ったことは何か
- 家庭地域との連携をどのようにとっていくか
- 家庭地域との連携がなぜ必要か
- 家庭地域との連携のためにどのような実践をしたか
面接の対応力を上げるには
教採は面接でいかに高得点を取るかが重要になってきます。
面接は
・配点が高い
・免除にならない
・自治体によっては、面接の点数順に一次合格になる
と、教採の中でも非常にウエイトの高い試験です。
どれだけ面接を攻略していくかが教採合格の鍵を握ります。
面接が苦手な人もいれば高得点を取る人もいますが、それぞれに共通していることがあります。
それは相手に好印象を持ってもらえるかどうかが大きな要因になっています。
どれだけ正確で深い知識をもっていても、悪い姿勢でボソボソ話していては印象としては悪く、合格は難しいです。
教採塾ブログでは専門スタッフによる面接練習をおこなっています。
A判定の取得経験のあるスタッフが面接練習をして
- あなたの長所と短所
- 短所の改善方法
- より面接官に伝わる面接の仕方
などをお伝えします。詳細は以下でご紹介しています。
また、面接で高得点を取る人、思った以上に点数が伸びない人。
それぞれの特徴については次の記事が大変参考になります。
無料で一部読めるので、ぜひ参考にしてみてください。
>>教採で落ちない面接 高得点を取る人の共通点と対策法

模擬授業
模擬授業の留意点など。
- 面接の中で実施
- 9分(構想2分、授業7分)
- 面接官2人
評価の主な観点
<模擬授業>
- 指導力
・授業を適切に進めていく基本的な指導技術があるか。
(発問、言葉がけ、板書、音声や声量等)
・児童生徒を惹きつける雰囲気や魅力があるか。 - 知識・理解
・指導内容についての基本的な知識があるか。 - 構成力
・指導のポイントやねらいが適切であるか。
・児童生徒が主体的に施行する場面を設定しているか。
・授業を適切に進めているか - 熱意
教えることに対する熱意や将来性を感じるか。
・「主体的・対話的で深い学び」を意識した教育実践への意欲が感じられるか。
・新たな教育課題や教育方法に挑戦(探究)しようとする姿勢はあるか。
<場面指導>
- 児童生徒の気持ちを理解しようとしていたか。
- 児童生徒の状況や年齢に応じて、関わりや声がけに工夫が見られたか。
- 指導の意図が明確に伝わったか。
- 児童生徒と信頼関係を築いていくような指導の仕方であったか。
<ロールプレイング>
- 入室時の児童生徒の表情や態度を見て、その子の気持ちに寄り添った言葉がけをしているか。
- 児童生徒の状況(けが等)に応じた適切な対応が落ち着いてできるか。
- 児童生徒の気持ちを理解しようとしているか。
- 気持ちを受けとめる温かい雰囲気があるか。
- うったえる様子等から児童生徒にどのような問題があるのかを理解しようとしているか。
過去の内容
- 小学校 第1学年 国語
「なつやすみのおもいでをなはそう」という単元において、児童が話題を決める学習を行います。この授業を導入から行ってください。 - 小学校 第4学年 算数
「およその数」の学習で。およその数の使い方や表し方について考える活動を行います。以下の例などを用いて、この授業を導入から行ってください。
【例】
きのうのテレビ放送では、サッカーの試合の入場者数を42816人と言っていましたが、今日の新聞には43000人と書いてあります。 - 小学校 第6学年 英語
「行ってみたい国や地域と、その理由」というトピックで「話すこと(発表)」を中心とした授業を行ってください。コミュニケーションを行う目的や場面、状況などは各自で設定してください。
なお、できるだけ英語を使ってください。 - 中学校 第1学年 国語
中学校1年生の国語の授業で「故事成語」について学習を行います。その授業を導入から行ってください。 - 中学校 第3学年 社会(公民的分野)
「商品の価格は、どのようにして決まっているのだろうか」を学習課題とし、消費生活を中心とした経済活動の意義について学習を行います。その授業を導入から行ってください。 - 中学校 第2学年 数学
「文字を用いた式」を学習しています。二つの奇数の和は偶数になることを説明する問題を扱った授業を行ってください。 - 中学校 第1学年 理科
植物の体の共通点と相違点についての学習は前時までに終わっているものとします。「動物の体の共通点と相違点」の学習の授業を行ってください。 - 中学校 第2学年 英語
「日本の伝統行事」というトピックで「話すこと(発表)」を中心とした言語活動を行うことにしました。コミュニケーションを行う目的や場面、状況などを設定したうえで授業を行ってください。また、小・中学校の学びの接続および連続性の観点に留意して授業を行ってください。
なお、授業は基本的に英語w用いることとします。 - 中学校 第1学年 美術
「身近な人へのプレゼントの包装紙をデザインする」とした題材について、導入部分の授業を行ってください。 - 中学校 第3学年 保健体育「保健」
「感染症の予防」の学習について授業を行ってください。 - 特別支援学校 小学部 知的障がい 単一障がい 生活単元学習 児童4名
地域住民に指導を受けながら、野菜栽培に取り組みました。収穫した野菜を使ったカレーライス作りの、導入部分の授業を行ってください。 なお、自分の意見や考えを一方的に話してしまう児童が1名います。 - 特別支援学校 小学部 知的障がい 単一障がい 特別活動 児童3名
3日後に実施することを予告している避難訓練(地震)と関連させて、安全について考える授業を行ってください。 なお、急に大きな音がすることや、急な予定変更に強い不安を示す児童が1名います。 - ロールプレイング 小3女子
健康上の理由により、クラスで一人だけ弁当を食べていることを悩む児童への対応(毎朝、保健室に弁当を預けている設定) - ロールプレイング 高3女子
交際相手との関係に悩む生徒への対応(デートDVの認識はない生徒) - 栄養 小学校 低学年(第2学年)
給食時間におかずだけ食べて、ご飯を残す児童が多い傾向にあると担任から相談がありました。これを受けて、学級全体に食事の食べ方について指導してください。 - 栄養 中学校(第2学年)
個別指導の場面で、肥満傾向にある生徒に対し、減量の必要性と、食生活のポイントについて指導してください。
授業後の質問
- 授業をしての感想
- 授業における目標
- (グループ活動をしたことから…) グループ協議をする際に大切にすること
- この後の授業の展開は
- 授業での工夫は
- 授業で伝えたかったことは
- 人権同和の授業で大切にしたいことは
- ノート指導で意識していることは
- 学力を向上させるためにはどうすればよいか
- 理科好きの子どもに育てるためには
- 授業のなかで大切にしていること
- 学校全体と道徳の関連をどう考えているか
- 間違えた子へのフォローはどうしているか
- いつ個別指導するか
- 遠足は特別活動の何に位置づけられるか
- 特別活動のねらいは

島根県はいたるところで「ふるさと」という言葉を目にします。それだけ「ふるさと教育」に力を入れている証拠です。県の出している資料を調べ、島根県の教育への理解を深めていきましょう。
島根県公立学校教育職員人材育成基本方針
島根県教育大綱
過去問についてはこちらで公開されています。
過去の試験問題と回答例
この記事を書いた人

- 教採塾ブログ管理人
- 教採対策サークル主宰
- これまでに多くの合格者を輩出
- 教員経験 小学校・中学
X:https://twitter.com/isshi_ec
教採情報や教員お役立ち情報を発信
フォローよろしくお願いします。
公式LINEでも教採に役立つ情報を発信中。
お友達追加するだけで対策資料4つを
🎁無料プレゼント🎁
ぜひお友達登録をお願いします😃